今回の記事の内容を動画でもお伝えしています。
・記事を読む時間がない
・家事をながらで聞きたい
・お子さんと一緒に聞きたい
という方は動画でボクが解説します☆
だいたい1.25倍速~1.5倍速で聞くとちょうど良いテンポです。
Contents
勉強する前に、道具を準備しよう!
まずは文房具を用意していきましょう。
道具がないと勉強できませんからね☆
①どっちがいいの?「シャーペン」と「えんぴつ」

ボクは「えんぴつ」でも「シャーペン」でもどちらでも構いません。
だって、学校じゃないし☆
ただし、
濃さはBかHBにしてください。
「シャーペン」でも「えんぴつ」でもどちらでもOK!
でも、芯の濃さはBかHBがオススメ!
ちなみに芯の硬さは柔らかいものから順に
6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、F、H、2H、3H、4H、5H、6H、7H、8H、9HB
「ブラック=黒い」、
Hは「ハード=かたい」ですね。
ボクのオススメは「B」です。
濃く、はっきりした字を書いて欲しい!
だから、
濃いめの芯をおススメしています。
「Bだと黒くなりすぎる」という子は筆圧が強い子です。
だから
「HB」の方がいいですね。
低学年で筆圧が弱い子は「2B」を使ってみるのもいいですね。
高校生ならいざしらず、
小・中学生で「H」を使っているのはおすすめしません。
芯の太さは0.5mmでも0.3mmが一般的です。
どちらでもいいのですが、ボクは0.5mmです。
大した理由はありません。
0.3mmってつまりやすくて、壊れやすい気がするんですよね(T ^ T)
もうひとつ言えば・・・
万が一、
シャーペンの芯がなくなったときに、友達に貸してもらいやすいってメリットがあります。笑
あ、意地汚いですね(;ω;)
②おすすめノートはA罫線7mm ドット付き

小学生低学年なら方眼マスのノートを使っている人も多いかもしれませんが、高学年になってきたら「横線だけのノート」に慣れていきましょう。
算数や数学では方眼マスだと途中式が書きにくくなってきます。
英語は方眼マスじゃ難しいでしょう。
そこでボクのおすすめは
『A罫線7mm ドット付き』
です。
ノートの大きさはB5でもA4でもどちらでも構いません。
ボクのこだわりは「A罫線7mm」です。
多くの人は「B罫線6mm」を使っているかもしれませんね。
でも、行の幅が広い方が見やすいです。
とくに小さな字を書くのが苦手な人、字が汚い人は「A罫線7mm」の方が圧倒的にいいです。

ボクが重視しているのは見やすさです。
よく勉強を見ていて多いのが
ギッチギチに書いている子
こういった子は
ケアレスミスも多いです。
解き方はわかっているのに、
ケアレスミスをするから、また解き直し。
結局、それは時間のムダになります。
だから、
ケアレスミスを防ぐためにも大きな文字で見やすさを重視してくださいね。
あと、最近は「ドット付き」というものもあります。
ドットがあると線がひきやすく、図も書きやすいです。
ドット付きがあればそれをオススメします。
これがあると問題番号などそろえる時に便利なんですよ☆
今は100円ショップにもあるので、そちらの方がいいでしょう。
あと注意してほしいのは、
ノートメーカーがいろんなノートを出しています。
ですが、
結論はドット付き以上の余計なものはいりません。
文房具店に行くと「理系ノート」「文系ノート」など細かく分かれています。
ボクは逆に使いにくく感じます。
ごちゃごちゃしすぎっo(`ω´ )o
ドットがあればそれで十分です。
忘れちゃいけないのが、
ノートは教科ごとに、分けて使ってください。
たまに、国語のノートと数学のノートをごっちゃに書いている人がいますが、それは良くありません。
別のノートを準備してください。
例えば、数学なら、
問題集によってノートを変えた方がいいですね。
『学校の授業を写すためのノート』
『学校の問題集を解くノート』
『塾のテキストを解くノート』
というように、同じ科目でも、問題集に分けてノートを作っておいてください。
③色ペンに役割を持たせよう

色ペンは
赤ペン
青ペン
緑ペン
の3色で十分です。
必要以上にカラフルにする必要はありません。
ノートは
「記憶の一時的な保管場所」
です。
全部覚えてしまえば、ノートなんかいらないわけです。
極端に言えばそういうことなので、ノートを必要以上にデコる必要はありません。
大切なのは
ノートに書いた内容を覚えて、いつでも思い出せること
これを忘れないでくださいね。
女の子に多いのですが、
時間をかけて、とてもカワイイノートを作っているのですが、肝心の中身を覚えていない。
それはあまり意味がありません。
ですが、
さすがにシャーペンだけだとインパクトが弱すぎです。
これは男の子に多い傾向です。
水墨画かっ!
ってくらい、黒いノート。
インパクトが弱いと、記憶しにくいのです。
だから、
色ぺんを使いましょう。
そのために色分けをして印象度合いを高めておきましょう。
色ペンを使う目的は3つ
- インパクトを強くする
- 重要度の順位をつける
- パッと見でわかるようにする
インパクトを強くするのは、先ほども言いましたね。
そして
この3本には大切な役割があります。
ここはゆっくり読んでください。
2つ目の大事なことは
重要度の順位をつけること
つまり、
色に役割を持たせるわけです。
各色の役割はこんな感じ。
赤ペン・・・重要項目
青ペン・・・スーパー重要項目
緑ペン・・・補足、付け足し、小ネタ
ボクが使っている色を参考にしてください。
実は「青色は記憶に残りやすい」のです。
青色を見ると冷静さを取り戻しやすいという特性があります。
脳が記憶に適した状態になります。
だから、
絶対に覚えておきたいところは青色でチェックです。
でも、
「全部覚えておかないと!」と思って全部真っ赤にするのはよくありません。
大事だと思ったところだけでいいです。
後から付け足すこともできます。
最初は本当の重要なところだけを赤で書きましょう。
ボクの授業で使う色も、これらの色とリンクしているので参考にしてください。
最後の3つめ。
大切なことを言いますね。
こうやって色によって重要度を決めておくことで
ノートを書きながら、
何が大切かを判断しながら勉強できるようになります。
受け身の勉強ではなくなるのです。
授業のときに、何も考えず先生のことばを書き写す。
一見、マジメに勉強しているように見えますが、成績は上がりません。
ただ、写しているだけですから。
そうならないように、
「大事だけどわかっているな〜」ってことは黒文字にしたり、黒板に書かれていないけど、先生が言った大事なことは青文字にして書いておく。
問題を解く時のヒントになったり、暗記を助ける語呂合わせは緑文字にしておくのもいいでしょう。
色を使わなさすぎるのもダメ!
むやみやたらに色を使うのもダメ!
色を決めておくことで
- 受け身の勉強にならない
- 何が大切なのかを判断できるようになる
色の役割を決めて、勉強効率をアップしましょうね♪
④消しゴムの注意点

消しゴムはぶっちゃけなんでもいいです♪
スタンダードなものならいいでしょう。
無難にMONOにしておけば間違いはないです。
ただし、
これだけはやめてください。
- におい付き消しゴム
- シャーペンの頭についているミニ消しゴム
におい付き消しゴムってなんだか消しにくい気がするんですよね。
なんか固いというか・・・。
におい付き消しゴムは小学3年生で卒業です(笑)
あと、
ボク的に絶対にやめてほしいのは
シャーペンの消しゴム
意外と多くの子がシャーペンのミニ消しゴムで消してるんです。
も〜〜〜( ・з・)
絶対にやめてほしい!
理由は
「消し残し」が起きるからです!
知ってますか?
あのシャーペンの消しゴムって、「普通の消しゴム」と違うんですよ。
普通の消しゴムって
プラスチック製品と一緒にしておくと溶けてくっついてしまう。
でも、
シャーペンの消しゴムってくっつかないじゃないですか?
その理由は消しゴム自体が違う材質だからです。
もう少し詳しく言うと、
「普通の消しゴム」ってプラスチック製で、紙の繊維の隙間に入って、鉛筆の粒子を吸着してとっているんです。
でも、
「シャーペンの消しゴム」はゴム製で、紙の表面を削りとって消している。
だから、
紙の繊維の隙間に入った粒子は取れないから、しっかり消せないのです。
だから、
シャーペンの消しゴムは最終手段です。
試験のときに
「消しゴムがな〜〜い!」
ってときだけ使ってください。
シャーペンの消しゴムは使わない!
究極の最終手段!
ボクがなぜここまでシャーペンの消しゴムを嫌うのかというと、
消し残しを絶対にして欲しくないからです。
消し残しは
- ノートが汚くなる。
- 式が見にくくなる
- ケアレスミスの元
- 採点者に誤解を与える可能性が高い
ようするに
消し残しがあると、ミスが起こりやすいのです。
成績がいい人たちは、
それを経験のうちに知っています。
正直、
きれいに消すのはめんどくさいですよ。
でも、
きれいに消さずにケアレスミスになる方がもっとめんどくさい。
だから、
きれいに消える消しゴムでていねいに消してくださいね☆
こういった細かいことを意識しておくと、ケアレスミスが減りますよ( ^ω^ )
⑤ものさしでミスを減らしましょう

必須です。
成績が良くない子って雑なんですよ。
雑でもまあまあ成績がいい子はいます。
でも、
ケアレスミスが多かったり、わかっていたのに解けなかったと言うことが多い。
そう言う子は
ノートの使い方が雑です。
ノートの使い方は
別の機会でお話ししますから、そちらを参考にしてくださいね☆
ていねいに書く
やっぱり、これが基本です。
図や表も「ものさし」を使って、書いてください。
長さを測るためじゃなくて、真っ直ぐな線を引くためです。
真っ直ぐな線を引くって意外と難しいんです。
大人ならそこまで苦労しませんが、子どもは真っ直ぐの線を描くことも難しい。
だから、
ものさしを使って、線を引いてください。
ものさしは長さを測るよりも
真っ直ぐな線を引くため
ここでひとつだけお伝えしておきます。
小学校、中学校のときはものさしを使うことをオススメします。
ですが、
高校生になると、ものさしを使わないようにしましょう。
図も表もすべてフリーハンドで描きます。
なぜなら、
大学入試では「ものさしは使ってはいけないから」です。
何年か前に
国語の入試の時にものさしを使って全科目無効になった人がいました。
禁止事項にも書かれています。
だから、
小学生、中学生のうちは「まっすぐ線を描く」ということを身につけて、高校から「ものさしを使わなくても図や表を描ける」ようにしておくのがいいですね。
小・中学生のうちは図や表をていねいに描く
高校生からは基本的にフリーハンド
コンパスや分度器は家に置いておけばいいですが、普段から持ち歩く必要はありません。
コンパスは意外と重いし、分度器は筆箱に入らないですしね。
必要な時だけ持っていけばいいと思いますよ。

文房具は絶対に必要な道具。
でも、文房具にこだわるよりも、こだわるのは使い方だよ。
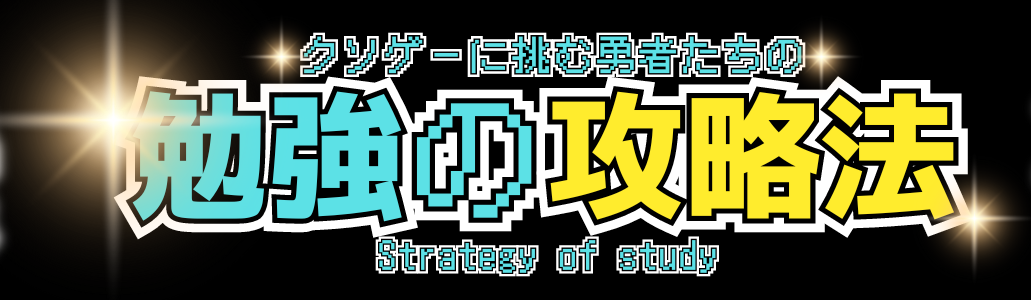
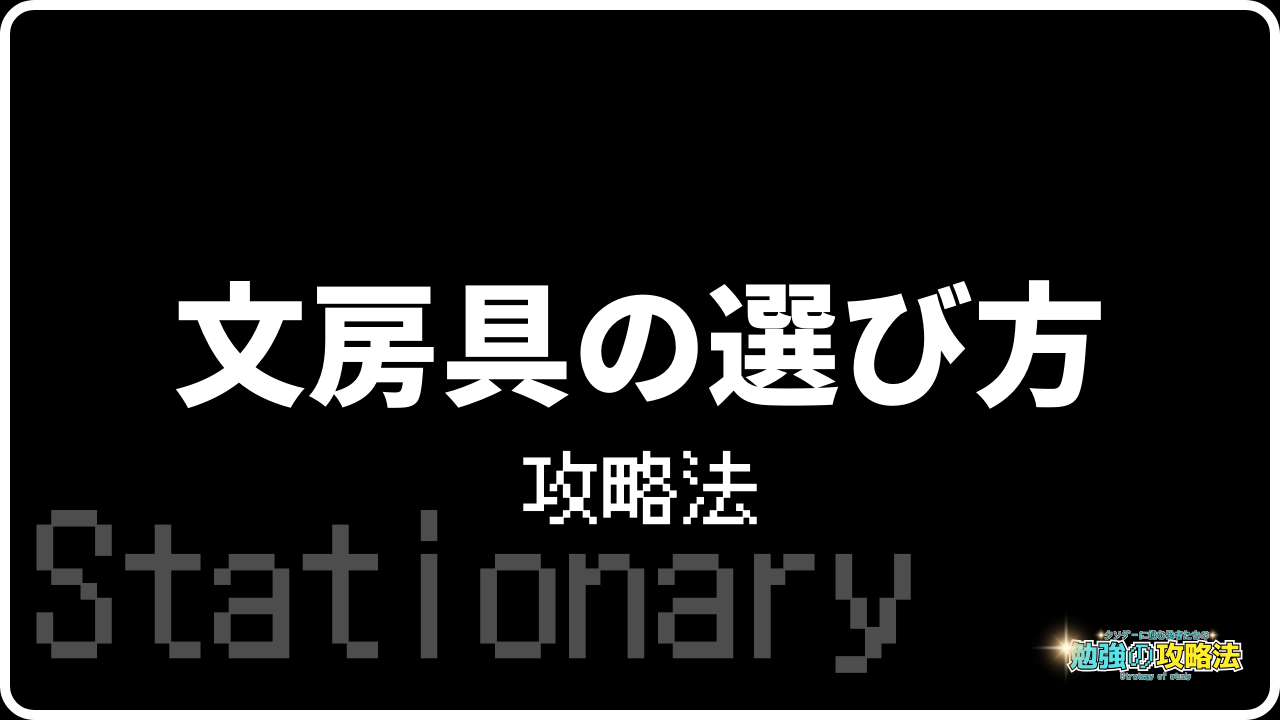
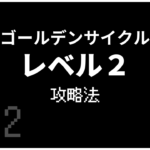
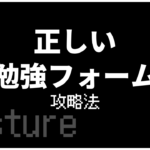
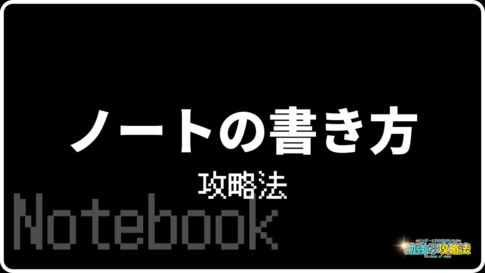

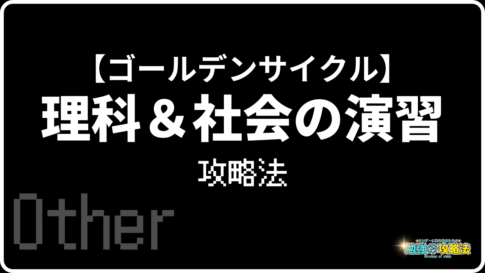
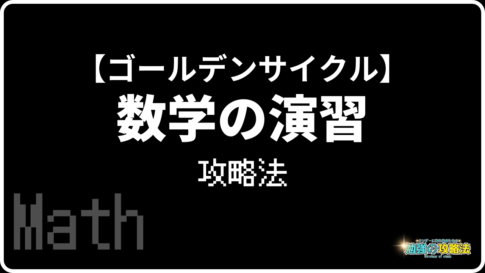
-485x323.jpg)

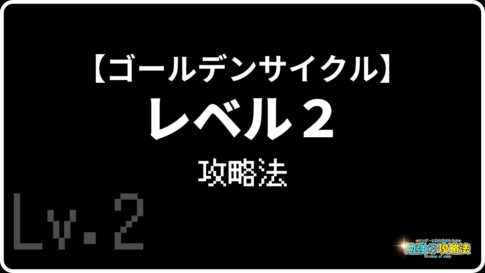
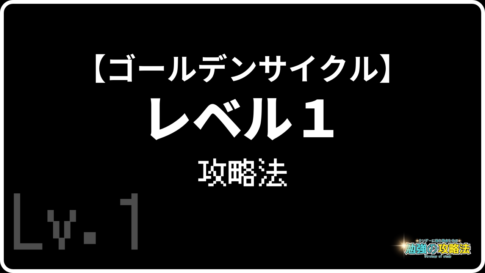
オススメノートはA罫7mm
見やすさ重視でケアレスミスを防ぎましょう。